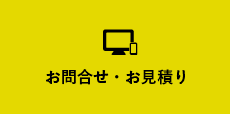2025.8.20

「人手不足が深刻で、生産ラインの維持が難しくなってきた」「設備を省人化したいが、どこから手をつければいいか分からない」
──そんな製造現場の悩みに、協働ロボットや自動化機器による省人化は有効な打ち手となります。
本記事では、実際に省人化を導入した企業の成功事例や、導入時の注意点、コストダウンと生産性向上を両立させるためのポイントをわかりやすく解説。
また、補助金の活用や、設計〜施工〜保守まで一貫して支援できる体制を持つ「松本電気工事有限会社」ならではの強みも交えながら、現場に最適な省人化の進め方をご紹介します。
「なるべく失敗せず、効果のある省人化を進めたい」とお考えの方に、きっとヒントをお届けできるはずです。
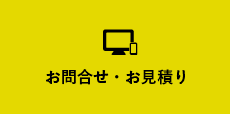
1. 協働ロボットとは?産業用ロボットとの違いを解説
1.1 協働ロボットの定義と特徴
協働ロボットとは、人間と同じ空間で安全柵なしに協働作業を行うことを目的として設計されたロボットを指します。従来の産業用ロボットが人間と隔離された空間で稼働するのに対し、協働ロボットは人間が隣接して作業できる点が最大の特徴です。
国際的な安全規格であるISO 10218-1/2(ロボットおよびロボット装置−安全要求事項)や、協働ロボットに特化した技術仕様であるISO/TS 15066(協働ロボット)に準拠しており、人間の安全を最優先に設計されています。
主な特徴としては、以下のような点が挙げられます。
- 高い安全性:
人間との接触を検知するとすぐに停止する力覚センサーや、人間の動きを認識して衝突を回避するビジョンシステム、設定された速度や力の上限を超えないように制御する機能などを搭載しています。これにより、万が一の接触時にも人間への危害を最小限に抑えることができます。
- 容易なティーチング:
専門的なプログラミング知識がなくても、ロボットアームを直接動かして動作を教え込む「ダイレクトティーチング」や、グラフィカルなインターフェースを用いた直感的な操作で、簡単に作業内容を教えることができます。これにより、導入後の運用負担が大幅に軽減されます。
- 柔軟な設置性:
安全柵が不要なため、省スペースでの設置が可能です。また、移動も比較的容易なため、生産ラインのレイアウト変更や多品種少量生産への対応が柔軟に行えます。
- 人間との協調性:
人間が得意とする判断力や器用な作業と、ロボットが得意とする精密さ、繰り返し作業、力仕事を組み合わせることで、生産効率と品質を同時に向上させることが可能です。
1.2 従来の産業用ロボットとの違い
協働ロボットと従来の産業用ロボットは、その設計思想、安全性、用途において明確な違いがあります。以下の表で主な違いを比較します。
| 比較項目 |
協働ロボット |
従来の産業用ロボット |
| 安全性と設置環境 |
人間と同じ空間で安全柵なしに協働作業が可能 |
人間と完全に隔離された空間(安全柵内部)での稼働が必須 |
| 人間との協働性 |
可能。人間の作業を補助・連携する設計 |
原則不可。高速・高負荷作業のため危険 |
| 主な用途 |
人間との連携作業、多品種少量生産、検査、ピッキング、組立補助など |
高速・高精度な定型作業、重量物の搬送、溶接、塗装など |
| プログラミング・ティーチング |
ダイレクトティーチングなど直感的で容易 |
専門的なプログラミング知識が必要 |
| 可搬重量 |
比較的小型・軽量(数kg〜20kg程度が主流) |
大型・高重量(数百kg〜1トン超も) |
| 設置スペース |
コンパクトで省スペース |
広い設置面積が必要 |
| 導入の柔軟性 |
生産ラインへの組み込みやレイアウト変更が容易 |
一度設置すると変更が困難な場合が多い |
従来の産業用ロボットは、高速かつ高精度な繰り返し作業や、人間には危険な重労働・単純作業を自動化するのに適しています。一方、協働ロボットは、人間の判断力や柔軟な動きと連携しながら、作業の自動化や効率化を図ることを得意としています。この違いを理解することが、適切なロボット選定の第一歩となります。1
2. 協働ロボット導入メリットの核心!生産性向上とコスト削減
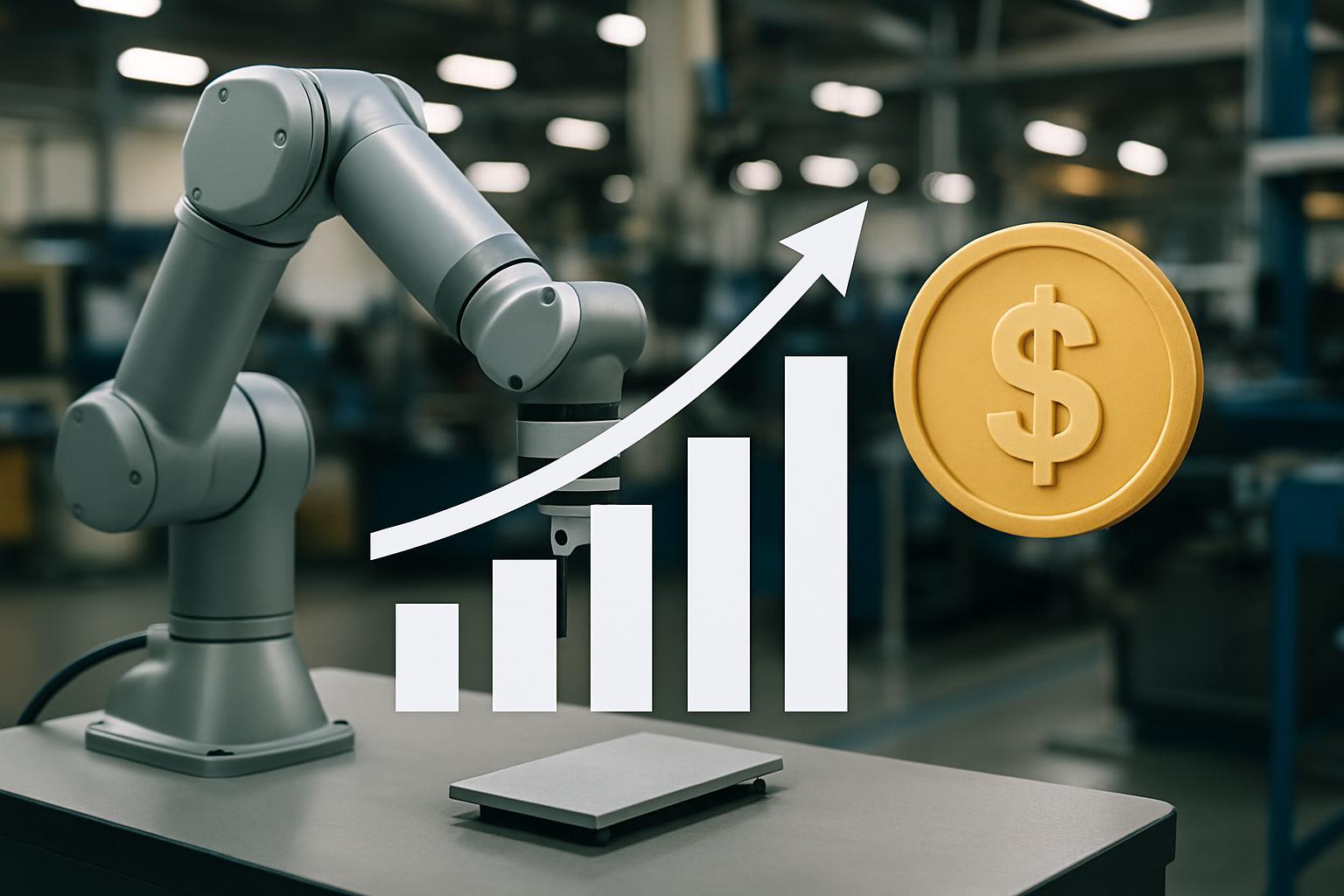
協働ロボット導入の最大の目的であり、企業にとって最も直接的な恩恵となるのが、生産性の飛躍的な向上と、それに伴うコストの削減です。人手不足が深刻化し、市場競争が激化する現代において、これら2つの要素は企業の持続的な成長に不可欠な基盤となります。協働ロボットは、従来の産業用ロボットにはない柔軟性と導入の容易さで、これらの課題解決に貢献します。
2.1 生産性向上と効率化
協働ロボットは、人間との協働を前提とした設計により、従来の自動化では難しかった領域での生産性向上と効率化を実現します。これにより、企業はより多くの製品を、より少ない時間とリソースで生産できるようになります。
2.1.1 作業の自動化によるスループット向上
協働ロボットは、繰り返し性の高い単純作業や、人間には負担の大きい重労働などを自動化するのに非常に適しています。これにより、生産ラインにおけるボトルネックが解消され、製品のスループット(単位時間あたりの生産量)が大幅に向上します。
例えば、部品のピッキング、組み立て、検査、梱包といった反復作業をロボットが正確かつ高速に実行することで、人為的なミスを削減し、生産サイクルタイムを短縮できます。結果として、より多くの製品を市場に供給できるようになり、売上増加に直結します。
2.1.2 24時間稼働と人手不足解消
人間には休憩や睡眠が必要ですが、協働ロボットは基本的に24時間365日稼働が可能です。これにより、夜間や休日も生産ラインを停止させることなく稼働を継続でき、工場の稼働率を最大化できます。特に、需要の変動が激しい時期や短納期が求められる生産において、その効果は絶大です。
また、近年深刻化する労働力不足、特に製造業における人手不足は多くの企業にとって喫緊の課題です。協働ロボットを導入することで、これまで人手に頼っていた作業を代替し、省人化を実現できます。これにより、採用難や人件費の高騰といった問題への有効な対策となり、安定した生産体制の維持に貢献します。
2.1.3 熟練作業者の負担軽減と人材有効活用
協働ロボットは、熟練作業者が行っていた単純作業や、肉体的に負担の大きい作業を肩代わりします。これにより、熟練作業者は重労働から解放され、より高度な判断を要する業務、品質管理、生産ラインの改善活動、あるいはロボットの監視やティーチングといった付加価値の高い業務に集中できるようになります。
これは、熟練作業者のモチベーション向上や、貴重なノウハウの伝承にも繋がります。企業は限られた人材をより戦略的に配置し、個々の能力を最大限に引き出すことで、組織全体の生産性と競争力を高めることができます。
2.2 コスト削減と投資対効果
協働ロボットの導入は、初期投資だけでなく、その後の運用においても様々なコスト削減効果をもたらし、結果として高い投資対効果(ROI)を実現します。
2.2.1 省スペース設計と安全柵不要による設置コスト削減
協働ロボットは、従来の産業用ロボットと比較して、小型かつ軽量なモデルが多く、省スペースでの設置が可能です。さらに、人間と協働することを前提とした安全設計が施されているため、適切なリスクアセスメントと安全対策を行うことで、多くの場合、高額な安全柵の設置が不要となります。
この安全柵が不要であるという点は、設置面積の削減だけでなく、設置工事にかかる費用や時間の大幅な削減に直結します。工場内のレイアウト変更も容易になり、生産ラインの柔軟な再構築が可能になるため、将来的な拡張や多品種少量生産への対応コストも抑えられます。
| 項目 |
協働ロボット |
従来の産業用ロボット |
| 安全柵の要否 |
不要(リスクアセスメントによる) |
必須 |
| 設置面積 |
省スペース(人間と同じ空間で作業可能) |
広大な設置面積が必要(安全確保のため) |
| 設置工事費用 |
低減(安全柵設置工事不要、電源工事など) |
高額(安全柵設置、基礎工事など) |
| レイアウト変更の容易性 |
高い |
低い(大規模な工事が必要な場合が多い) |
2.2.2 ティーチングの容易さによるプログラミングコスト削減
従来の産業用ロボットの導入において、専門的なプログラミング知識を持つ技術者によるティーチング(動作教示)は、導入コストの中でも大きな割合を占める要素でした。しかし、協働ロボットは、直感的なダイレクトティーチングや、タブレット端末を用いたグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)による操作が可能です。
これにより、専門的なプログラミング知識がない現場の作業員でも、簡単にロボットに動作を教え込むことができます。外部の専門業者に依頼する費用や、社内での教育コストを大幅に削減できるだけでなく、急な生産品目の変更や作業内容の調整にも迅速に対応できるようになり、生産の柔軟性が向上します。
| 項目 |
協働ロボット |
従来の産業用ロボット |
| ティーチング方法 |
ダイレクトティーチング、タブレット操作、GUI |
専用のプログラミング言語、ティーチングペンダント |
| 専門知識の要否 |
不要(直感的、初心者でも操作可能) |
必須(専門知識、熟練した技術者が必要) |
| 習得難易度 |
低い |
高い |
| プログラミングコスト |
低減(内製化可能、外部委託費用削減) |
高額(専門家への依頼、人件費) |
2.2.3 ランニングコストの低減とROI最大化
協働ロボットは、初期投資だけでなく、導入後のランニングコストにおいても優位性を持っています。一般的に、協働ロボットは低消費電力で稼働するため、電気代を抑えることができます。また、シンプルな構造と堅牢な設計により、メンテナンスの頻度が少なく、維持管理費用も低減されます。
さらに、人件費の削減効果と24時間稼働による生産量増加は、売上向上と利益率改善に直結します。これらの複合的な効果により、協働ロボットの初期投資は比較的短期間で回収され、高い投資収益率(ROI)を実現することが可能です。長期的に見れば、協働ロボットは企業の収益性を大きく向上させる強力なツールとなります。
3. 協働ロボットがもたらすその他の導入メリット

3.1 協働ロボット(URロボット)による作業代替
省スペースで安全柵なしに人と共に働ける「協働ロボット(URロボット)」は、省人化の第一歩として多くの現場で導入が進んでいます。
組立、検査、梱包といった繰り返し作業に最適で、柔軟にラインに組み込むことが可能です。
松本電気では、現場診断から設置・プログラム設定・操作教育まで一貫対応。「初めてのロボット導入で不安」という現場にも、専任技術者がしっかり伴走し、即戦力化を支援しています。
3.2 自動搬送・リフター・AGVなどの物流効率化
重量物の搬送や部品供給といった物流工程は、人手に頼ると負担も事故リスクも大きくなります。AGV(無人搬送車)やAMR(自律移動ロボット)、自動リフターを活用することで、運搬作業の自動化・効率化が可能になります。
松本電気では、導入する機器だけでなく、通路幅・電源・センサー配置なども考慮した「工場レイアウト再設計」までサポート。 既存設備との共存を前提に、段階的な自動化を支援します。
3.3 画像検査AIや自動化ソフトとの連携活用
外観検査工程は自動化が難しいとされてきましたが、画像認識AIの進化により、省人化が急速に進んでいます。微細なキズや異物混入も高精度に検出可能で、人の目を超える精度が実現できます。
松本電気では、画像検査AIと協働ロボットを組み合わせたライン構築や、PLC・センサー連携の自動制御設計にも対応。 ハード・ソフト一体での導入支援が可能です。
4. 協働ロボット導入メリットを最大化する活用事例

協働ロボットの導入メリットは、業種や企業規模を問わず、具体的な現場で大きな成果として発揮されています。
ここでは、中小企業から大企業まで、多様な業界における協働ロボットの成功事例を紹介。
導入検討の具体的なイメージを掴んでいただくための参考になれば幸いです。
4.1 協働ロボットによる工程自動化(長野県 金属加工業 A社の事例)
長野県の金属加工業A社では、組立・検査工程において高齢作業者の負担が大きく、人手不足も深刻でした。
同社は、URロボットを活用して、部品供給や目視検査工程の一部を自動化。 安全柵不要の協働ロボットを既存ラインに導入することで、省スペースのまま稼働を実現しました。
このような省人化のアプローチは、松本電気でも「現場診断 → 最適なロボット選定 → 設置・制御・操作教育」まで一貫して対応可能です。既存ラインに負担をかけずに導入できる点は、多くの製造業様にとって現実的な選択肢となるでしょう。
4.2 多品種生産におけるAI活用(自動車部品メーカー B社の事例)
B社では、多品種少量生産体制において、段取り替えや部品認識の属人化が課題でした。
そこで、画像認識AIと産業用ロボットを組み合わせたシステムを構築。製品ごとの自動認識と自動工程切り替えにより、ミス削減と効率化を同時に達成しました。
松本電気では、画像AIやFAソフトウェアとロボットの連携構築にも対応可能です。こうした他社事例をもとに、現場ごとのニーズに応じた最適なシステム設計をご提案できます。
4.3 AMRによる内部物流の自動化(精密機器製造 C社の事例)
C社では、工場内の部品搬送に人手と時間がかかっていたため、AMR(自律移動搬送ロボット)を導入。
生産指示と連動した自動搬送により、搬送作業を80%削減・誤搬送ゼロを実現しました。
松本電気では、AMRやAGVの選定から、搬送ルート設計、配線・制御・安全対策まで一貫対応可能。 製造現場における内部物流の自動化にも柔軟に対応しています。
5. 協働ロボット導入成功へのポイント
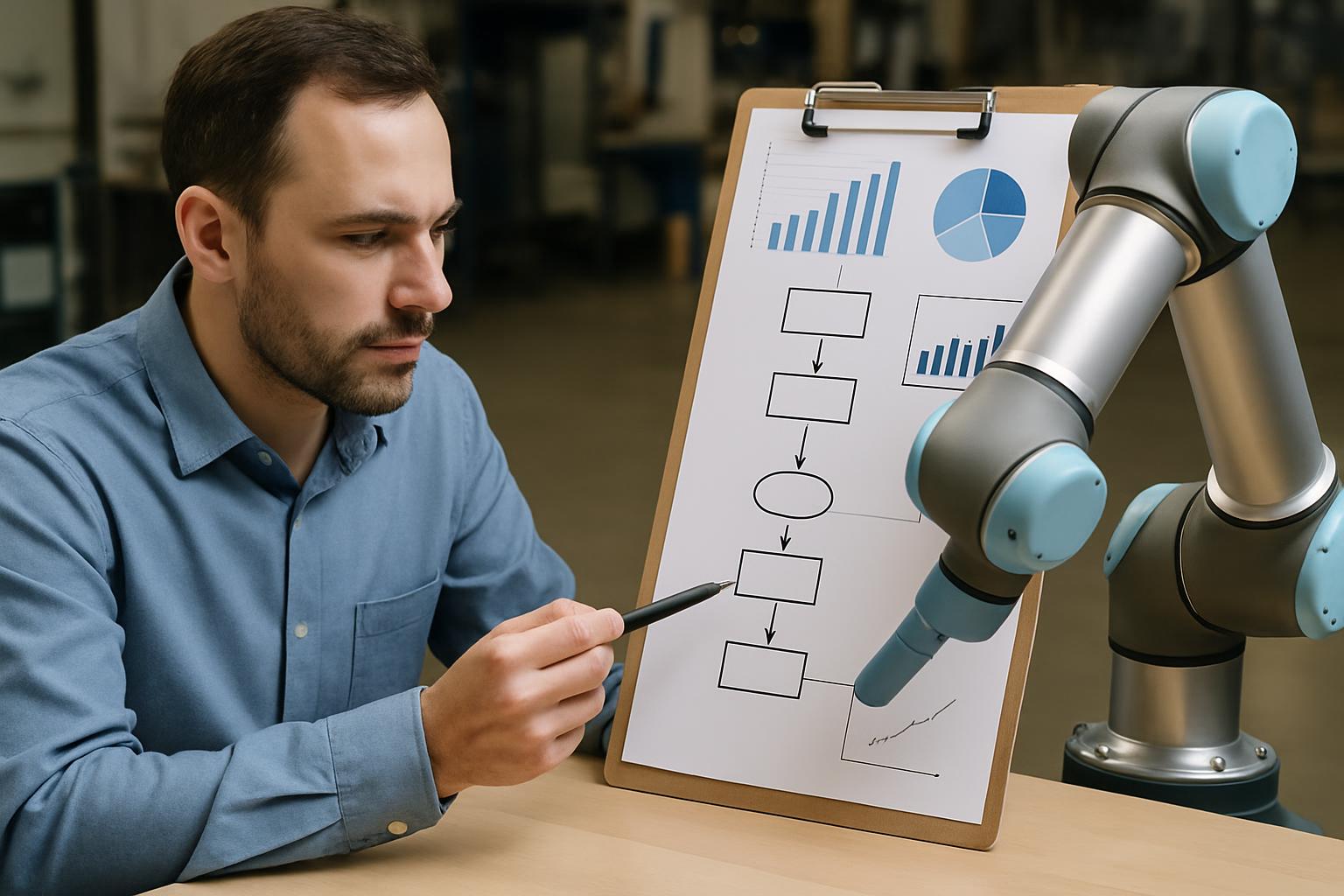
協働ロボットの導入は、企業の競争力強化に大きく貢献しますが、その成功には計画的なアプローチが不可欠です。漠然とした導入ではなく、具体的な目標設定から運用体制の確立まで、各段階で押さえるべきポイントを解説します。
5.1 導入目的の明確化と課題特定
協働ロボット導入の第一歩は、「なぜ導入するのか」という目的を明確にすることです。現状の課題を具体的に洗い出し、それに対する協働ロボットの有効性を評価することで、導入後のミスマッチを防ぎ、最大の効果を引き出すことができます。
5.1.1 具体的な目標設定
導入目的は、単に「自動化したい」ではなく、数値目標として具体的に設定することが重要です。これにより、導入後の効果測定が可能となり、投資対効果(ROI)の評価も容易になります。
| 導入目的の例 |
具体的な目標(KPI)の例 |
期待される効果 |
| 生産性向上 |
生産量20%アップ、タクトタイム10%短縮 |
スループットの向上、納期短縮 |
| コスト削減 |
人件費15%削減、残業時間30%削減 |
運用コストの低減、収益性の改善 |
| 品質向上 |
不良品率5%削減、検査精度99.9%達成 |
製品品質の安定化、顧客満足度向上 |
| 安全性向上 |
危険作業からの解放、労働災害ゼロ |
作業環境の改善、従業員の安全確保 |
| 人手不足解消 |
特定の工程での人員配置最適化、採用コスト削減 |
既存人材の有効活用、事業継続性の確保 |
5.1.2 現状分析と課題の洗い出し
目標設定と並行して、導入を検討している工程や作業の現状を詳細に分析し、課題を洗い出します。現場の作業者からのヒアリングや、作業時間の計測、不良発生原因の特定など、多角的な視点での分析が不可欠です。
- どの工程にボトルネックがあるか?
- どのような作業が危険、または重労働か?
- 熟練作業者の技術に依存しすぎている作業はないか?
- 人手不足により生産計画が滞るリスクはないか?
- 多品種少量生産への対応が困難な状況はないか?
これらの課題を具体的に特定することで、協働ロボットが最も効果を発揮する導入箇所を見極めることができます。
5.2 適切な機種選定とシステム構築
導入目的と課題が明確になったら、次にそれらを解決するための最適な協働ロボットと周辺システムを選定し、構築する段階に入ります。単にロボット本体を選ぶだけでなく、全体的なシステムとしての整合性を考慮することが重要です。
5.2.1 ロボット本体の選定
市場には様々な協働ロボットが存在します。導入目的や作業内容に合致した機種を選定するためには、以下の要素を総合的に評価する必要があります。
| 選定基準 |
考慮すべき点 |
| 可搬重量 |
取り扱うワーク(対象物)の最大重量に適しているか |
| リーチ(動作範囲) |
作業エリア全体をカバーできるか、周辺機器との配置を考慮 |
| 精度・繰り返し精度 |
要求される作業品質(例:部品の挿入、塗布など)を満たせるか |
| 安全機能 |
衝突検知、速度監視、力制限などの安全機能が充実しているか、国際安全規格(ISO 10218-1/2、ISO/TS 15066など)に準拠しているか |
| ティーチングの容易さ |
現場でのプログラミング変更が容易か、直感的な操作が可能か |
| 設置スペース |
既存の生産ラインや作業スペースに収まるか、省スペース設計か |
| メーカーサポート |
導入後の保守・メンテナンス体制、技術サポートの充実度 |
| 導入実績 |
自社の業界や用途での実績があるか、類似事例の有無 |
複数のメーカー(例:ユニバーサルロボット、ファナック、安川電機、川崎重工業、デンソーウェーブなど)の製品を比較検討し、デモンストレーションやトライアルを通じて実際の性能を確認することが望ましいです。
5.2.2 周辺機器・システムの構築
協働ロボット単体では、その能力を最大限に引き出すことはできません。作業内容に応じた適切な周辺機器やシステムとの連携が不可欠です。
- エンドエフェクタ(ハンド、グリッパー、ツールなど): ワークの種類や作業内容(把持、吸着、溶接、研磨など)に合わせた最適なものを選択します。
- ビジョンシステム・センサー: ワークの位置決め、品質検査、バラ積みピッキングなどに活用し、ロボットの柔軟性と精度を高めます。
- 供給装置・排出装置: ワークの自動供給や完成品の排出を効率化し、連続稼働を可能にします。
- 制御盤・安全機器: ロボットシステム全体の制御、非常停止ボタン、安全エリアの監視など、安全かつ安定した運用に不可欠です。
- 既存設備との連携: 既存のコンベア、加工機、検査装置などとの連携を考慮し、スムーズなデータ通信や信号のやり取りを実現します。
これらのシステム構築には、専門知識を持つシステムインテグレーター(SIer)の活用が非常に有効です。SIerは、お客様のニーズに合わせて最適なシステム設計から導入、運用支援までを一貫してサポートし、導入リスクを低減します。
5.3 社内体制の整備と人材育成
協働ロボットの導入は、単に機械を設置するだけでなく、それを運用する社内の体制と人材の準備が成功の鍵を握ります。新しい技術への理解と、それを使いこなすためのスキル習得が不可欠です。
5.3.1 運用体制の構築
協働ロボットを安定的に運用するためには、明確な役割分担と責任範囲を定めた体制を構築する必要があります。
- 導入プロジェクトチームの立ち上げ: 企画、開発、生産、保守など、関連部署からメンバーを選出し、情報共有と意思決定を迅速に行える体制を構築します。
- 担当部署・責任者の明確化: ロボットシステムの日常的な運用、トラブル対応、メンテナンスを担当する部署や責任者を明確にします。
- 運用マニュアルの作成: ロボットの起動・停止、日常点検、エラー発生時の対処法などを網羅したマニュアルを作成し、作業者全員がアクセスできるようにします。
- 定期的なメンテナンス計画: 故障を未然に防ぎ、システムの寿命を延ばすために、定期的な点検・保守計画を策定し、実施します。
また、導入後も生産計画や市場の変化に合わせて、柔軟にロボットのタスクを変更できる体制を整えることが、協働ロボットのメリットを最大限に活かす上で重要です。
5.3.2 技術者・作業者の育成
協働ロボットを安全かつ効率的に運用するためには、操作・保守に関わる人材の育成が不可欠です。ロボットに対する理解を深め、スキルを向上させることで、現場での自律的な運用が可能になります。
| 育成内容 |
具体的なスキル・知識 |
育成方法の例 |
| 基本操作・ティーチング |
ロボットの起動・停止、安全機能の理解、簡単な動作のティーチング、プログラムの呼び出し |
メーカー研修、SIerによるOJT、社内勉強会 |
| プログラミング・調整 |
複雑な動作プログラムの作成・修正、センサーや周辺機器との連携設定、精度調整 |
専門研修機関での受講、メーカー提供のプログラミング講座 |
| トラブルシューティング |
エラーコードの解読、簡単な故障診断、復旧手順の理解 |
運用マニュアルの活用、メーカーサポートとの連携訓練 |
| 保守・メンテナンス |
日常点検、消耗部品の交換、定期的なグリスアップ、異常の早期発見 |
メーカー提供のメンテナンスガイド、経験豊富な技術者による指導 |
| 安全教育 |
協働ロボットに関する安全規格(ISO 10218-1/2、ISO/TS 15066など)の理解、リスクアセスメントの実施、非常停止手順の習得 |
安全衛生講習、実機を用いた安全訓練 |
特に、作業者の心理的な抵抗を解消し、ロボットとの協働に前向きになってもらうためのコミュニケーションも重要です。ロボットが「仕事を奪う」存在ではなく、「仕事を助け、負担を軽減する」パートナーであるという理解を深めることが、スムーズな導入と定着につながります。
6. 松本電気工事の支援体制:省人化を成功に導くパートナーとして

製造現場の省人化を進めるうえで、「どこから始めればいいのか分からない」という声を多く耳にします。
私たち松本電気工事は、そんな現場のリアルな悩みに寄り添いながら、“最適な自動化”を一緒に考える存在です。
省人化の成功は、単にロボットや機器を入れればいいという話ではありません。
「何が課題か」「どこまで自動化できるか」──まずは現場の声を丁寧に拾い上げることから、私たちの支援は始まります。
6.1 現場の声から始める「診断型のご提案」
松本電気工事では、機械や電気設備の知見をもつ専門エンジニアが現場を直接訪問。
実際の作業フローや人員配置を見ながら、「自動化できるポイント」「手作業のまま残すべきポイント」を丁寧に見極めていきます。
また、投資効果やスケジュール感も一緒に可視化し、ご担当者が社内に説明しやすいようサポート資料もご用意しています。
「現場を知っているからこそ、現場にフィットする提案ができる」──これが私たちの強みです。
6.2 ワンストップ体制で“現場にフィットする導入”を実現
私たちは、ロボットの選定から、制御盤設計、配線、機器設置、安全対策まで、すべて自社内で対応できる技術体制を整えています。
「実際に導入してみたら、思ったより大がかりだった」「安全対策が不十分だった」
──そんな失敗を防ぐためにも、松本電気では現場とのすり合わせを徹底し、柔軟な施工や調整が可能です。
また、協働ロボットやAMRなど、操作に慣れていない方も多いため、操作レクチャーやマニュアル整備、安全教育までサポートします。
「現場で“使いこなせる状態”まで持っていくこと」までが、私たちの導入支援です。
6.3 導入して終わりじゃない。“その後”に寄り添う運用支援
機器の導入後も、「調子が悪い」「工程を変えたい」といったご相談はつきものです。
松本電気では、定期点検やトラブル対応、稼働状況の改善提案まで、導入後の運用支援にも力を入れています。
また、生産量の変化や工程追加などがあっても、「段階的に自動化を進めたい」「新しいラインにも展開したい」といった要望にも柔軟に対応可能です。
私たちは、現場の“困った”を一番に聞けるパートナーであり続けたいと考えています。
📌こんなときは、ぜひご相談ください
- 現場にロボットを入れたいが、何から始めていいかわからない
- 人手が足りない工程があるが、全自動は難しそう
- 安全対策やレイアウト変更まで含めて相談したい
- 補助金や助成金をうまく活用したい
松本電気工事は、人と機械が無理なく共存できる省人化の実現を、現場目線で支援します。
まずはお気軽にご相談ください。