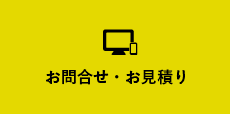2025.7.25

工場の省人化を検討中の方へ―本記事では、少子高齢化による人手不足やコスト高騰といった課題を解決する最新の自動化設備、成功事例、導入時のポイントをわかりやすく解説。
導入効果と具体的な進め方が明確に分かります。
🔽松本電気へのお問い合わせはこちらから🔽
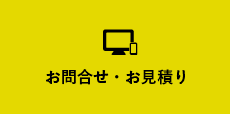
1. 工場に省人化が求められる背景とは?
1.1 なぜ今、省人化が必要なのか
近年、日本の製造業を取り巻く環境の変化が加速しています。
特に労働人口の減少に伴う深刻な人手不足や、労務コストの上昇が顕著となり、「従来の人海戦術に頼る生産体制」には限界が見え始めています。
そのため、多くの工場では生産性向上の切り札として省人化への取り組みが拡大しています。
さらに、新型コロナウイルス流行を契機に、製造現場における感染症リスクの低減や、柔軟で持続可能な生産体制の構築が求められるようになり、省人化・自動化の重要度が格段に高まっています。
1.2 人手不足とコスト高騰への現実的対策
厚生労働省や経済産業省の調査結果によると、製造現場で慢性的な人手不足に悩む企業は8割以上にのぼります。
とりわけ中小企業では、従業員の高年齢化や若年層の人材確保難が深刻化しており、「現有社員への過剰な負担」「採用・教育コストの増加」など、複数の課題が同時並行して発生しています。
また、エネルギー価格や材料費の高騰にともない、企業経営を圧迫する大きな要因となっています。
| 課題 |
現在の状況 |
省人化導入の目的 |
| 人手不足 |
有効求人倍率の高止まり・従業員の高齢化 |
人材確保に依存しない生産体制を実現する |
| 人件費増加 |
最低賃金の上昇・採用と教育のコスト増 |
作業効率向上と固定費の圧縮 |
| 競争力の維持 |
生産性の鈍化・他社との価格競争 |
自動化による品質とスピードの向上 |
| 安全・健康面への配慮 |
過重労働・感染症リスク |
作業環境の改善と安全対策の強化 |
このように、省人化の推進は単なるコスト削減にとどまらず、「持続可能な生産」と「競争力強化」の双方を実現するうえで不可欠な施策となっています。
企業規模を問わず、ロボット・AI・IoTなど最新技術を活用した省人化へのシフトが、将来の成長と安定経営を左右するカギを握っています。
2. 工場の省人化がもたらす主なメリット

工場の省人化は、単なる作業の自動化以上のメリットをもたらします。
人材不足やコスト高騰など、現代の製造業が直面する課題への根本的な解決策となりつつあり、さらに企業の競争力向上にも寄与します。
以下では、主なメリットを詳しく解説します。
2.1 人件費の削減と生産性の向上
省人化を推進することで、従来よりも少ない人員で同等またはそれ以上の生産量を維持・拡大できるため、人件費の圧縮が可能です。
自動化設備や協働ロボットの導入によって、交代勤務や残業への依存度が減少するほか、繁忙期・閑散期の波動にも柔軟に対応できます。
特にライン作業や反復工程では、自動機が安定した稼働を提供し、労働生産性の大幅な向上に繋がります。
| カテゴリ |
省人化前 |
省人化後 |
効果 |
| 人件費 |
年間3,000万円 |
年間2,000万円 |
約30%削減 |
| 生産数 |
1日500個 |
1日700個 |
約40%増加 |
| 人員 |
10名 |
6名 |
作業者4名分省力化 |
2.2 品質の安定と作業者の安全性向上
自動化技術による省人化は、人による作業のバラツキを抑え、常に均一な品質を実現できる大きなメリットがあります。
画像検査AIや自動計量機・溶接ロボット等を導入することで、「不良品の発生率低減」や「検査工程の見える化」が進み、不良原因の早期発見につながります。
また、重作業や危険作業の代替として自動搬送装置や協働ロボットを導入することで、作業者の安全リスクを大幅に軽減し、労働災害の発生防止と作業環境の改善を同時に実現できます。これは製造業の労働安全衛生マネジメントにおいても重要なポイントです。
| メリット項目 |
期待できる効果 |
| 品質の安定 |
ロボットや自動検査装置による不良率低減・品質ばらつきの防止 |
| 安全性向上 |
重量物搬送や薬品取り扱いなどの危険作業の自動化による事故リスク低減 |
| 従事者への配慮 |
過重労働や単純反復作業から解放し、働きやすさ・定着率向上に貢献 |
3. 省人化に役立つ主な設備・ソリューション

3.1 URロボット(協働ロボット)による作業代替
近年、協働ロボット(コボット)は省人化を推進する代表的な自動化技術として注目されています。特にユニバーサルロボット(URロボット)は、その安全性・柔軟性・プログラミングの簡易さから、日本国内の多くの工場で採用が進んでいます。
従来は自動化が難しかった組立・検査・梱包などの細かな工程でも、協働ロボットが人に代わり作業することで作業効率が向上し、ライン全体の生産性アップに貢献します。また、安全柵なしで人と同じ空間で作業できるため、既存ラインへの導入も容易です。
| 導入メリット |
適用例 |
主な特徴 |
| 人員削減・作業品質均一化 |
部品組立、ねじ締め、検査補助 |
省スペース設置・安全設計 |
3.2 自動搬送・リフター・AGVなどの物流効率化
物流部門の省人化には無人搬送車(AGV・AMR)や自動リフターなどの搬送自動化システムが効果的です。
原料や製品、部品の運搬作業は人手による重労働であり、ミスや事故のリスクも伴います。
AGVはラインと倉庫間、工程間の単純反復搬送を無人で行うことが可能で、経路の最適化やリアルタイム監視システムと組み合わせることで、工場全体の物流効率を大幅に高めます。AMR(自律移動ロボット)を導入することで複雑な工場レイアウトにも柔軟に対応でき、少量多品種生産に適した効率的な自動搬送を実現できます。
| 設備種類 |
主な用途 |
活用効果 |
| AGV(無人搬送車) |
原材料搬送、製品出荷ライン搬送 |
運搬時間短縮・ヒューマンエラー削減 |
| 自動リフター |
重量物の持ち上げ・積み替え |
安全性向上・作業負担軽減 |
| AMR(自律移動ロボット) |
多拠点間の自律搬送 |
レイアウト変更対応・省人化柔軟化 |
3.3 画像検査AIや自動化ソフトとの連携活用
検査工程の省人化では、AI画像検査システムと自動化ソフトウェアの連携活用が重要な役割を担っています。
画像認識AIは製品の外観検査や欠陥品の発見、人間の目では発見困難な微細な不良も高精度で検出可能です。
さらに、このAI検査装置を協働ロボットや専用搬送システムと連動させることで、完全自動の検査・仕分けラインが構築され、検査人員ゼロ実現も可能になります。
実際に、電子部品・自動車部品・食品工場など幅広い分野で品質保証と省人化の両立を実現しています。
| ソリューション |
導入事例 |
メリット |
| 画像検査AI(キーエンス・オムロン等) |
微細な傷・異物混入検査 |
検査精度向上・人為ミス削減 |
| 自動化ソフト(PLC・MES連携) |
工程監視・設備制御の自動化 |
データ活用・効率的運用管理 |
4. 成功事例に学ぶ!工場の省人化導入事例

工場の省人化を実現するには、現場の実情に合わせた自動化設備やデジタル技術の適用が不可欠です。
ここでは、実際に国内の製造業で成果を挙げた具体的な成功事例を、導入の経緯や効果、工夫点までわかりやすく整理してご紹介します。
4.1 金属加工工場での協働ロボット導入
かつて人手で行われていた部品の機械加工や組立作業を、協働ロボット(URロボット)によって自動化した事例です。
東京にある中堅金属加工メーカーA社では、慢性的な人手不足と熟練工の高齢化対策が課題でした。
社内で移動や部品セットなど単純反復作業を洗い出し、URロボットを導入。ロボットは人作業者と近接して安全フェンスなしで稼働し、部品供給や検査工程を担う仕組みを構築しました。
| 導入前の課題 |
導入ソリューション |
得られた効果 |
| 単純反復作業で人手不足、熟練工の負担増 |
協働ロボット(UR3e)による部品移載と検査の自動化 |
人件費15%削減、歩留まり向上、不良発生率が半減 |
このように安全柵なしで既存ラインに簡単に協働ロボットを追加できた点が、省スペースの現場にも適合した好事例です。
4.2 多品種少量生産の自動化対応
自動車部品メーカーB社(愛知県)は、多品種少量生産の生産体制で、切替や段取りのたびに多くの人手を要していました。
産業用ロボットと画像認識AIを連携させることで、品種ごとに異なるワークの識別や自動段取り替えを可能にしました。
AIがカメラ映像からワーク種類を瞬時に判別。FAシステムと連動してロボットが最適ツールを選択し、自動で作業工程を切り替えます。
| 導入前の課題 |
導入ソリューション |
得られた効果 |
| 多品種対応の人手切替、ミス・手待ち時間が多い |
AI画像検査とロボットによる自動品種判別・工程切替 |
作業ミス95%減、切替時間60%短縮、生産性25%向上 |
AIとロボットを統合することで多品種少量生産現場でも省人化と高効率生産を両立した点が特徴です。
4.3 AMRによる部品供給の自動化事例
千葉県の精密部品製造C社では、従来、部品供給や完成品の搬送に現場作業者が毎日長時間を割いていました。
これを最新のAMR(自律走行搬送ロボット)により自動化。 AMRは工場内の部署間を地図・センサーに基づいて安全かつ自律で移動し、部品や製品の所定位置への配送・回収作業を実施します。
また、生産管理システムと連携することで、ピッキング指示も自動発行される運用へ移行しました。
| 導入前の課題 |
導入ソリューション |
得られた効果 |
| 現場作業者の搬送作業負荷・運搬ミス |
AMR導入と生産管理システム連携による自動部品供給 |
搬送作業工数80%削減、作業者の肉体負担軽減、誤搬送ゼロ |
人が担っていた内部物流業務をAMRが自律的・安全に行うことで、ものづくり現場の効率・正確性向上に寄与しています。
以上のように、省人化の成功事例には「協働ロボットによる工程の自動化」「AIと連動した自動段取り」「AMRなどの自律搬送ロボットの活用」といった多様な切り口があります。
工場それぞれの課題や生産タイプに合わせて、機器・システムを最適化して導入し、段階的な省人化を進める姿勢が極めて重要です。
5. 省人化導入時に気をつけたい4つのポイント
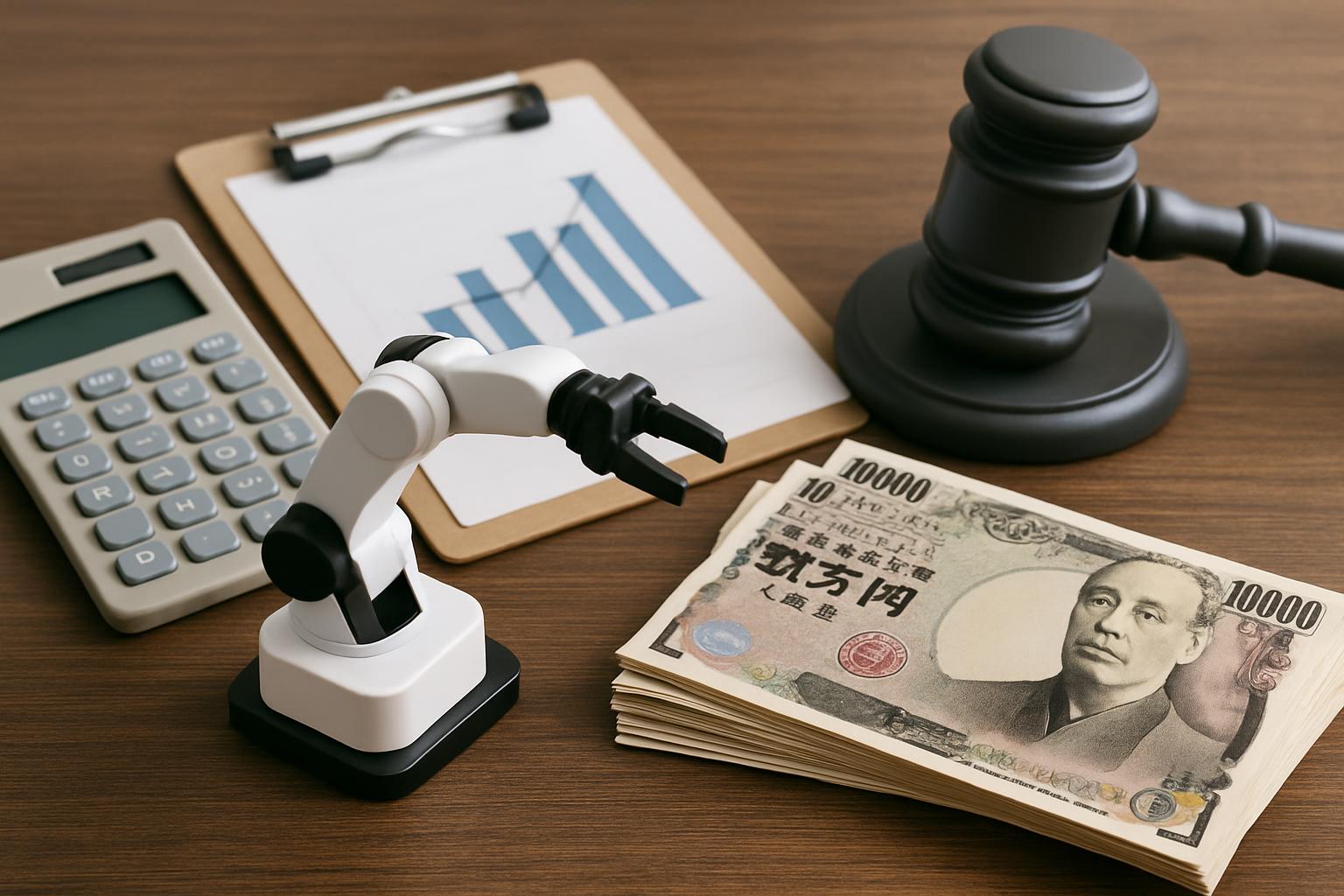
5.1 補助金・助成金の賢い活用方法
省人化設備の導入は初期費用が高額になりがちです。そのため、経済産業省や地方自治体が提供する補助金・助成金を活用することが不可欠です。
主な補助金には「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などがあり、申請には事前準備と要件の把握が求められます。
申請期間、必要書類、補助率などは案件ごとに異なるため、専門家や商工会議所に相談しながら手続きを進めることが大切です。
| 補助金・助成金名称 |
特徴 |
対象となる設備 |
補助率 |
| ものづくり補助金 |
中小企業の生産性向上やプロセス改善を支援 |
ロボット、自動化機器、ITシステム |
1/2~2/3 |
| IT導入補助金 |
ITツールやソフトウェアの導入支援 |
画像検査AI、MESシステム |
最大1/2 |
| 地域独自の助成金 |
自治体ごとに特色あり |
自動搬送車、AMRなど |
内容により異なる |
早めの情報収集とスケジュール管理も成功のポイントです。
5.2 従業員への説明と教育の重要性
省人化をスムーズに進めるには、現場の従業員理解と協力が必要不可欠です。
自動化設備は単純に機器を入れ替えるだけではなく、作業フローや役割分担も変化します。
導入前にしっかりと説明会を行い、メリットや安全性、新しい働き方について丁寧に周知しましょう。
現場レベルでのOJT(現場教育)、外部研修、マニュアル整備を組み合わせて実施し、「人が使いこなせる自動化」を目指すことが大切です。
| 教育内容 |
方法 |
ポイント |
| 操作方法 |
現場実習、動画教材 |
繰り返しの実習で定着を図る |
| 安全対策 |
座学、実地演習 |
ヒヤリハット事例の共有 |
| 故障時対応 |
実演トレーニング |
基本的なメンテナンス項目の習得 |
5.3 自動化に向く工程・向かない工程の見極め
全ての作業工程が自動化に適しているとは限りません。
繰り返し作業や単純物の搬送、検査作業は自動化と相性が良い一方、細やかな調整や複雑なバリ取り、非定型作業は自動化が困難な場合があります。
導入前には各プロセスを棚卸しし、工程ごとの自動化適性を客観的に評価しましょう。
| 工程の種類 |
自動化の向き・不向き |
理由 |
| 部品供給・搬送 |
向いている |
パターン化・標準化しやすい |
| 組立(単純作業) |
向いている |
反復作業が多い |
| 目視検査 |
部分的に向いている |
画像AIを活用できるが、複雑な検査は有人が必要 |
| 複雑な組立・調整 |
不向き |
高度な判断や臨機応変な対応が求められる |
初めての省人化には「成果が出やすい範囲」から着手し、段階的な拡大が成功のカギです。
5.4 安全設計と現場レイアウト再設計
省人化=安全性向上ではなく、新たなリスクも生まれます。
ロボットや自動搬送車の導入時には、衝突防止センサーや非常停止装置の設置、立ち入り制限エリアの明確化といった安全設計が不可欠です。
また、既存設備との干渉、導線の確保、作業スペースの最適化など、現場レイアウト全体を見直すことも重要です。
| 安全対策項目 |
具体例 |
ポイント |
| ロボットの安全柵 |
セーフティドア、閾値感知センサー |
作業者の誤侵入を物理的に防止 |
| 非常停止装置 |
押しボタン式・引き綱式スイッチ |
複数箇所への設置で即時停止 |
| 導線の確保 |
地面へのライン表示、歩行帯と搬送帯の分離 |
ヒューマンエラーの発生防止 |
定期的なリスクアセスメントと従業員からのフィードバック体制を作ることで、現場環境の安全性を高めることができます。
6. 松本電気工事の省人化支援:導入から保守までの流れ

製造現場における省人化の実現には、単なる機器導入にとどまらず、現場ごとに最適なプランニングと導入後の継続的なサポートが欠かせません。
松本電気工事は、産業現場での自動化・省人化分野において豊富な実績を持つ専門企業として、多様な要望に応えるワンストップ体制を構築しています。
ここでは、同社が提供する省人化導入の流れをわかりやすく解説します。
6.1 現場診断から最適設計の提案
松本電気工事では、まず現場ごとの業務分析・課題抽出からスタートします。
専任のエンジニアが直接工場を訪問し、工程ごとに人手作業・自動化可能範囲を丁寧にヒアリング。
生産ラインの現状や、お客様ごとの製造プロセスに最適化した機器・システムの選定を行います。
また、投資対効果や今後の拡張性も見据えたうえで、見積・導入計画を明確に提示します。
| 工程 |
主な内容 |
提供価値 |
| 現場診断 |
稼働状況・作業実態の把握、データ収集 |
省人化における効果予測と課題抽出 |
| 最適設計 |
自動化機器やロボットの選定、シミュレーション |
個別ニーズに合わせたカスタム設計 |
| ご提案 |
導入フロー、工程別の自動化可能性、費用シミュレーション |
導入後の費用対効果を可視化 |
6.2 ワンストップの機器導入・施工・教育
松本電気工事は、機器選定から設置・ネットワーク配線・制御盤工事・安全対策・システム構築まで、すべてを自社技術者によるワンストップ体制で対応しています。設置段階では営業・技術・現場スタッフが密に連携し、運用現場の実状に即した柔軟な対応が可能です。
さらに、省人化設備の導入やロボットの操作に不慣れな作業者向けに、現場での操作説明・安全教育・運用マニュアルの作成支援もきめ細かく実施。
導入したその日から生産現場で安定稼働できるよう、手厚いサポート体制を構築しています。
| 工程 |
詳細内容 |
| 機器納入・設置 |
協働ロボット・コンベア・AGV等の設置・配線 |
| 制御システム構築 |
PLCプログラム作成、IOT連携システム開発 |
| 現場教育 |
操作説明、安全講習、マニュアル作成 |
6.3 稼働後の運用支援とアフターメンテナンス
設備導入後のトラブル対応や生産性の定着こそが、省人化プロジェクト成功のカギとなります。
松本電気工事では、稼働後の定期点検、メンテナンス、ソフトウェア更新、ライン改修などのアフターフォローも重要視。
エラー発生時の迅速な現場対応や、稼働ログにもとづいた改善提案で、安定稼働と更なる効率化をサポートします。
また、省人化設備の追加導入や工場全体の統合管理など、将来的な拡張・生産体制の段階的な自動化にも柔軟に対応できるため、長期にわたってお客様の現場力強化に寄与します。
| サポート項目 |
具体的な内容 |
| 定期点検・保守 |
各種機器の動作点検、消耗品交換、異常予兆の早期発見 |
| トラブル対応 |
24時間体制での故障・不具合への緊急対応 |
| 運用改善提案 |
生産データ分析による追加自動化、工程最適化の提案 |
このように松本電気工事は、省人化導入にあたり現場診断・設計から導入、教育、アフターフォローまで一気通貫で支援。
大手メーカーから中小製造業まで幅広い業種で信頼され、省人化での生産性向上・コスト削減・品質安定の実現を力強くサポートしています。
🔽松本電気へのお問い合わせはこちらから🔽