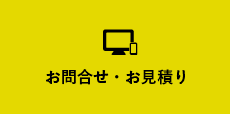2025.7.5

介護施設の停電対策やBCP義務化に対応するため、非常用発電機の導入と補助金活用は欠かせません。
この記事では、長野県で使える補助制度の最新情報から導入手順、注意点までを分かりやすく解説します。
松本電気へのお問い合わせはこちらから。
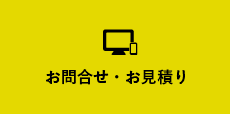
1. 介護施設に非常用発電機が必要な理由とBCP対策の重要性
1.1 災害時、停電が介護施設にもたらすリスクとは
長野県を含む日本全国では地震・台風・大雪などの自然災害が頻発しており、停電による介護施設への影響は無視できません。介護施設は高齢者や要介護者など自立が難しい方が多く、電力の停止は命に関わる重大なリスクとなります。
特に以下のような設備は電力供給が止まると重大な障害が発生します。
|
設備・システム
|
停電時の影響
|
|
ナースコール
|
緊急時の呼び出しや安否確認が不能に
|
|
給排水設備
|
トイレ・手洗いなどの水が使用不可に
|
|
空調・暖房設備
|
熱中症・低体温症などの健康被害リスク
|
|
医療用機器
|
酸素供給・吸引機など生命維持機器の停止
|
|
照明・非常灯
|
避難誘導や夜間の安全確保が困難に
|
このようなリスクを最小限に抑え、入居者や利用者の安心・安全を守るためにも、非常用発電機の備えは必須です。
近年では、災害拠点となる特別養護老人ホームやグループホーム、デイサービス施設への電源確保要請も高まっています。
1.2 BCP(事業継続計画)策定義務と非常用電源の位置づけ
2024年度から、介護サービス事業者にはBCP(事業継続計画)策定が義務化されています。
BCPは災害や感染症発生時にも、事業・サービスを継続するための計画であり、「電力の確保」はその最重要項目のひとつです。
特に介護施設では、BCP内で以下の観点が求められています。
|
項目
|
具体的な対応例
|
|
非常用電源の確保
|
施設の規模・必要電力に応じた発電機の設置
|
|
重要機器の優先運用
|
医療機器や通信設備など優先順位の明確化
|
|
燃料備蓄計画
|
非常用発電機駆動のための燃料量・保管方法の整備
|
|
定期メンテナンス
|
発電機の動作確認と点検体制の構築
|
こうした事業継続力強化のため、地方自治体や厚生労働省も補助金制度を設け、非常用発電機導入を推奨しています。
災害時のリスク軽減と法令遵守、そして利用者の命を守るために、発電機導入は介護施設運営の重要な柱となっています。
2. 長野県の介護施設で使える発電機補助金制度【2025年最新】

長野県内の介護施設が非常用発電機を導入するにあたり活用できる主な補助金は、国や自治体が交付する制度が中心です。2025年度に申請できる最新情報をもとに、各補助金の概要やポイントを解説します。
申請要件や支援内容、補助対象設備の条件など複数ありますので、要点ごとに分かりやすくまとめました。
2.1 厚生労働省「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の概要
厚生労働省が実施している「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」は、介護施設の安全・安心な運営や災害対応力強化を目的とした補助事業です。この交付金では、非常用発電機の整備費用が補助対象になっています。
特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホームなど多様な介護事業所が活用できます。
|
補助対象
|
主な補助内容
|
2025年度助成率/上限額
|
|
認知症高齢者グループホーム
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設 など
|
非常用発電機の設備整備費
BCP導入関連費用
|
定額または定率(目安1/2~2/3)
金額は施設規模や予算により異なる
|
申請は各自治体を通じて行う必要があります。
交付金の詳細な配分や対象事業所は、年度ごとの公募要項の公表を待って確認しましょう。
2.2 長野県・市町村の独自支援制度(2025年度予定含む)
長野県および各市町村では、国の交付金と連動・補完するかたちで、介護施設の防災設備導入や老朽化対策に対する独自補助を実施しています。
2025年度についても、同様の非常用発電機導入助成事業の継続が予定されています(一部は予算・要件調整中)。
|
自治体名
|
主な補助内容
|
補助率・上限額
|
主な要件
|
備考
|
|
長野県全域(県事業)
|
発電機設置費、付帯工事費、メンテナンス費
|
1/2以内(上限100万円)
|
BCP策定、国交付金との併用が前提
|
年度により変更あり
|
|
松本市、長野市ほか
|
独自補助枠、災害対策機器整備
|
自治体により異なる
|
自治体が定める施設区分・要件あり
|
例年は先着順受付が多い
|
2025年度は能登半島地震など大規模災害の教訓を受けて、防災強化関連予算が増額される見込みです。必ず最新の自治体ホームページや担当窓口で情報を確認してください。
2.3 補助対象となる発電機の条件と注意点(ポータブルは対象外 etc.)
補助金で認められる非常用発電機には、明確な基準があります。補助対象となる主な要件を一覧にまとめます。
|
条件
|
ポイント・詳細
|
|
出力・容量
|
施設の避難スペースや医療器具、冷暖房、通信機器などBCPに明記された最低必要電力を24時間以上確保できること
|
|
設置形態
|
据置型の業務用(屋内・屋外問わず固定式)
簡易、移動用のポータブル発電機は多くの場合、不可
|
|
認定
|
国内基準(JIS、消防法等)を満たし、点検・整備体制が確保できるもの
|
|
管理体制
|
日常の保守・定期点検、燃料供給計画、運転要員訓練等の運用体制も補助金活用の審査項目となる
|
メーカーや機種によっては対象外となるケースがあるため、計画段階で事前確認を徹底しましょう。
2.4 補助金活用に必要なBCP策定のポイント
発電機導入補助金の交付には、介護施設独自の「BCP(事業継続計画)」策定が必須となっています。
策定したBCPの内容が、発電機の仕様や配置、非常時運用計画と連動している必要があります。
- BCPには、災害発生時の電力維持計画と発電機の運用・燃料備蓄計画を盛り込む
- 入所者の命を守るための最低限必要な設備(照明・医療器具・通信)の電源供給体制を明記
- 停電発生時の対応手順や、職員の役割分担、訓練計画も具体的に記載
長野県や自治体では、BCP策定支援セミナーやアドバイザー派遣なども行っており、補助金申請とあわせて積極的な活用をおすすめします。
3. 介護施設の発電機導入と補助金申請の進め方

3.1 ステップ① 施設の電力ニーズと機種選定
介護施設における非常用発電機の選定は、まず自施設の電力使用状況を正確に把握することから始まります。
避難スペースや医療機器、給排水設備、通信機器など、停電時にも最低限稼働させるべき機器の必要電力量や稼働時間を見積もりましょう。
さらに、長期化する停電にも対応できるよう、燃料タイプ(ディーゼル、ガス、ガソリンなど)、必要な出力容量、設置スペースや騒音・排気規制も考慮に入れて機種を選定することが大切です。
3.1.1 必要電力量の算出例
|
機器名
|
消費電力(W)
|
必要台数
|
合計消費電力(W)
|
|
非常照明
|
100
|
20
|
2,000
|
|
医療用吸引器
|
200
|
2
|
400
|
|
給水ポンプ
|
1,500
|
1
|
1,500
|
|
通信機器
|
300
|
1
|
300
|
|
合計
|
|
|
4,200
|
これを基準に、さらに将来的な増設や使用時間なども見込んで選定を行うことが推奨されます。
3.2 ステップ② 補助金要件の確認と事前協議(自治体対応)
補助金を活用する場合、国や長野県、各市町村の補助要件を事前によく確認することが大切です。
特に「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」では、補助対象となる発電機の仕様(定置型であること、一定出力以上が対象など)が設けられています。
導入予定の発電機とその設置内容が要件を満たしているかを、自治体の福祉担当部署、または所轄の保健所等と早めに協議しましょう。事前協議を怠ると、あとで補助金申請が認められないケースもあります。
|
確認事項
|
主な内容
|
確認先
|
|
対象施設か
|
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム等
|
市町村福祉課
|
|
発電機の種類・仕様
|
定置型・出力基準・メーカー指定有無
|
県・市町村担当窓口
|
|
補助対象経費
|
本体・設置工事費・付帯設備費用等
|
補助金窓口
|
|
BCPとの整合性
|
事業継続計画における位置づけ
|
県庁、自治体担当
|
3.3 ステップ③ 申請書類の準備と提出スケジュール
補助金申請には、所定の申請書類や計画書、見積書、施設図面、BCP関連の資料などが必要です。
自治体ごとに提出フォーマットや必要書類が異なる場合もあるため、事前に最新の公募要綱を確認しましょう。
一般的な申請から交付までのスケジュールは次の通りです。
|
時期
|
作業内容
|
|
4月〜6月
|
要件整理・機種選定・自治体への事前相談
|
|
7月〜8月
|
申請書類作成・見積取得・BCPなど関係書類整備
|
|
9月〜10月
|
書類提出・自治体審査・質疑応答
|
|
11月以降
|
交付決定・事業実施・完了報告
|
多くの場合、事前申請が必要であり、交付決定後の着工となるため、スケジュールに余裕を持った準備が不可欠です。
3.4 ステップ④ 設置工事と補助金交付後の運用管理
交付決定を受けたら、契約締結、発電機や付帯設備の発注、施工会社による設置工事を進めます。
設置後は自治体担当者の完了検査等が行われることも多いため、施工の記録や関連書類を整備しておきましょう。
補助金交付後は、発電機が正しく運用されているか定期的な保守点検を実施し、万一の災害時に確実に稼働できる体制を維持することが重要です。
また、BCPにも運用計画や訓練・点検の内容を反映することで、より実効性の高い災害対策が可能となります。
4. 介護施設における発電機導入成功のポイントと注意点

4.1 ありがちな失敗例とその回避策
介護施設で非常用発電機を導入する際によく見られる失敗には、発電機の容量の誤算、設置場所の環境不備、補助金要件の誤認などがあります。
例えば、必要な電力量を正しく算出せずに小容量の発電機を導入してしまうと、停電時に全ての必須設備が稼働せず、BCP(事業継続計画)として機能しなくなるリスクがあります。
また、騒音や排気の問題を十分に考慮せず設置した場合、近隣や利用者に悪影響が出ることも考えられます。
これらの失敗を防ぐためには、導入初期段階で専門業者や自治体の担当窓口と相談し、現場見学や類似施設の事例も参考にしながら、必要容量や設置環境、補助金要件を丁寧に確認することが重要です。
また、補助金申請では「ポータブル発電機は対象外」など細かい制度ルールを必ずチェックし、導入後の運用体制まで見越した計画書を用意しましょう。
4.2 施工会社選びで重視すべきポイント
非常用発電機の設置工事は、高い信頼性と継続的なアフターサポートが求められます。
選定時は「介護施設における非常電源工事」の実績が豊富であるか、自治体や行政手続きにも精通しているか、万が一トラブル発生時に迅速な対応ができる体制があるかが大きなポイントとなります。
|
チェックポイント
|
具体的な内容
|
|
施工実績
|
介護・福祉施設に特化、BCP策定支援の経験有無
|
|
行政手続きサポート
|
補助金申請や自治体対応に精通したスタッフ配置
|
|
アフターサービス
|
定期メンテナンス、故障時の緊急対応体制、24時間サポート有無
|
|
環境対策
|
低騒音・低排気モデルの提案や、設置場所への配慮
|
|
見積り・説明の明瞭さ
|
費用内訳が明確で、分かりやすい説明を受けられる
|
複数社から見積りを取得し、上記ポイントを比較検討した上で、実際にサポート可能な範囲や実績も十分に確認しましょう。
4.3 災害時の“本当に役立つ”運用体制とは
発電機を備えるだけでなく、停電時に安全かつ迅速に稼働させる運用体制の整備も不可欠です。まず、稼働マニュアルを作成し、日常的な操作訓練・模擬訓練を職員全体に行き渡らせることが重要です。
また、発電機の燃料保管量を定期的に確認し、最低3日分は備蓄することが推奨されています。
さらに、対象となる設備リスト(照明、福祉用エレベーター、医療機器、情報通信機器など)や優先順位を予め明確にしておき、停電発生時に速やかに切替が行えるようにしておくことが大切です。
加えて、地元消防・行政や電気保守会社との連携体制を日常的に構築し、非常時の連絡手順も職員で共有しましょう。
運用体制の点検項目とベストプラクティスを以下のように整理しておきます。
|
運用体制項目
|
具体的な取り組み
|
|
定期訓練
|
年2回以上の発電機操作訓練、マニュアル更新
|
|
燃料備蓄
|
最低3日分の燃料確保と在庫管理台帳の作成
|
|
稼働記録
|
月次または四半期ごとの動作確認記録の保存
|
|
優先設備リスト
|
停電時に優先給電する機器とその手順書の整備
|
|
外部連携体制
|
地元消防・行政・保守業者の連絡網の整備と年次連絡会
|
こうした運用体制の構築は、発電機の導入効果を最大限に発揮させ、万が一の非常時にもご利用者の安心・安全を確保するために欠かせません。
5. 松本電機が提供する介護施設向け発電機導入サポート

5.1 補助金申請の支援・BCP作成サポート
松本電機では、介護施設向け発電機導入に関わる各種補助金申請の支援を行っています。
補助金の公募要項や申請書類の作成サポートだけでなく、補助対象要件に合致した内容での構成アドバイスも可能です。
また、最近では補助金申請の際にBCP(事業継続計画)の策定が申請条件となっているケースが一般的です。
松本電機では、介護施設の運営実態に合ったBCP策定の具体的なサポートも提供しています。
福祉施設に実際に求められるリスク洗い出しや対応策の整理、電源確保に関する緊急時対応マニュアルの作成など、実効性のある計画立案をワンストップで支援します。
5.2 発電機選定から設置まで一括対応
介護施設の規模や提供するサービス内容、必要限界電力、施設構造を十分に踏まえ、最適な非常用発電機を提案します。
ガス発電機やディーゼル発電機、インバーター式など多様なメーカー製品から選定し、台数、容量、燃料方式などの比較検討も専門スタッフが行います。
施設様の状況やご要望に応じて、段階的な対応も可能です。現場に即した柔軟なサポート体制を整えています。
|
導入ステップ
|
具体的な対応内容
|
|
現地調査・ヒアリング
|
施設の電力使用状況の測定、課題把握、現場の安全確認
|
|
機種選定・見積作成
|
必要電力から候補機器を選定。メーカーや型式ごとの比較提案
|
|
自治体との事前協議
|
補助金要件の確認、設置条件に関する行政との調整
|
|
申請書類作成
|
補助金申請書、設計図、スケジュール表等の準備と提出代行
|
|
設置工事・試運転
|
資格者による安全な据付工事、配線接続、動作確認
|
|
運用マニュアル作成・研修
|
非常時の操作マニュアルやBCP内運用手順の説明・従業員研修
|
5.3 地域密着型の迅速な対応と施工実績
松本電機は、長野県内に特化した営業体制を構築し、松本市はもちろん、安曇野市、塩尻市、諏訪市を中心に多くの介護施設様への非常用発電機納入実績があります。
信州エリア特有の気象や地形リスクも熟知しており、行政担当者との連携や設置基準への対応も万全です。
また、地元企業として、導入後の保守点検や緊急時の対応など、継続的に寄り添ったサポートにも力を入れています。
停電時のトラブル対応や年次点検体制も整えており、介護施設の安全と安心の維持に貢献します。
長野県内での主な施工実績は以下のとおりです。
|
施工エリア
|
主な施設種別
|
平均設置容量(kVA)
|
|
松本市・安曇野市
|
特別養護老人ホーム、グループホーム
|
20~50
|
|
塩尻市・諏訪市
|
小規模多機能型施設、老健施設
|
15~30
|
施設ごとの個別ニーズに合わせた柔軟な提案と、スピーディかつ確実な設置対応に努めており、安心してお任せいただける体制を整えています。
専門スタッフによる無料現地調査も承りますので、お気軽にご相談ください。
6. まとめ|発電機と補助金活用で介護施設の安心を守るために

災害時のリスク軽減と事業継続のため、長野県の介護施設では非常用発電機の導入が不可欠です。
国や自治体の補助金を活用し、要件や申請の流れを正しく理解することで、初期負担を抑えて安全性を高められます。
補助金の有効活用が、利用者と職員の安心を守る最善の選択です。
松本電気へのお問い合わせはこちらから